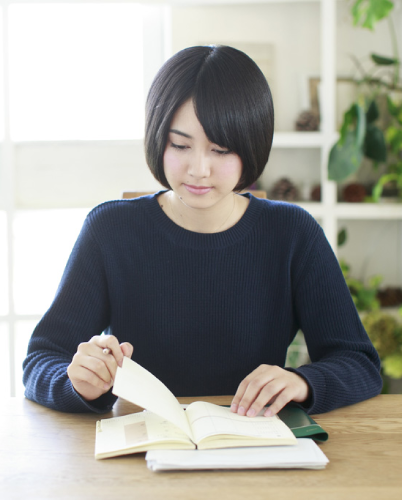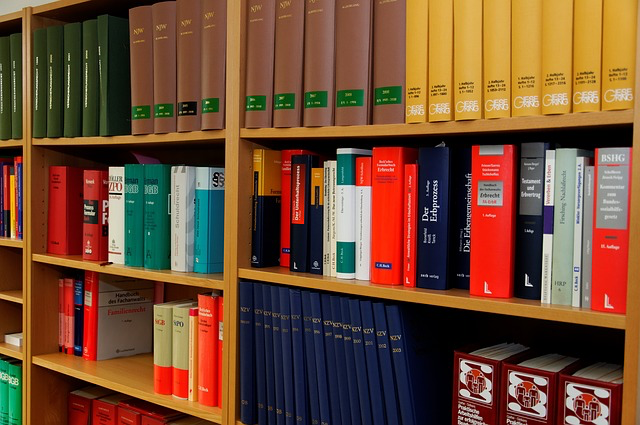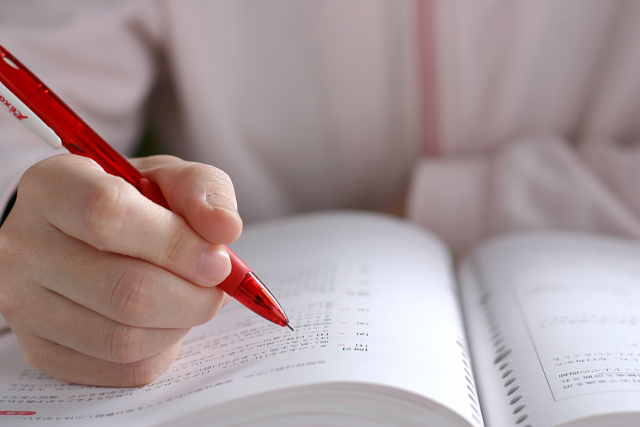宅建の個別指導 資格スクエア
宅建士は不動産関連のエキスパートとして、重要事項の説明、重要事項説明書面への記名と押印、37条書面(契約書面)への記名と押印などの業務を行うことができます。合格率は15~18%で推移しており、35点以上取れれば合格ラインを超えることができると考えていいでしょう。出題科目は宅建業法、権利関係、法令による制限、税法その他関連知識となっています。また、本試験の問題は過去問と類似した問題が非常によく出題されるため、過去問対策が最も有効な勉強法であると言えます。
攻略のコツ
個人によってばらつきはありますが、宅建試験の合格までに要する学習時間はおよそ350時間程度といわれています。これは1日に2時間ずつ勉強しても半年かかる計算です。
しかし、やり方次第ではこの時間を短縮することができるのです。宅建試験攻略の3つのポイントを見てみましょう。
過去問は「解く」のではなく「読む」
ほとんどの受験生は、まずテキストを読んで知識をインプットしてから問題を解くというやり方で勉強しています。実はこれは非常に効率の悪いやり方なのです。合格に必要なゴールが分からないまま勉強を始めては、結局どこを覚えるべきなのか分かりません。
まずは過去問を「読む」ことから始めましょう。問題と解説を並べて、問題を読んで、選択肢を読んで、解説を読むのです。
この段階で意識することは知識をインプットすることではなく、問題の傾向を知り、難易度を知り、出題者の意図を知ることです。過去問を何年分か読めばぼんやりとゴールが見えてくるはずです。
早く全体像をつかむこと
法律というのは特殊な学問で、全体像を把握しなければ理解できない部分があるのです。
ですので、勉強を進める際は分からない部分はどんどん飛ばしましょう。今は分からなくても大丈夫です。2周目の時には、1周目では分からなかった部分が分かるようになっているのです。
今までの勉強とはやり方が異なるので困惑する方も多いと思いますが、法律はそういうものだと割り切って勉強することが重要です。
過去問をひたすら解くこと
| 商品名 | 宅建士受験講座 |
|---|---|
| カテゴリ | 学習教材 |